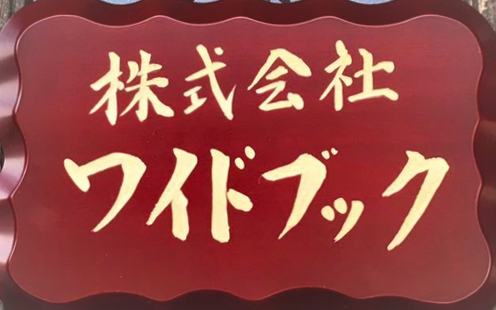地域の新規商品・サービス開発プロジェクト
1.目的と位置づけ
本プロジェクトは、農家と地域の人々が協力し、都市の人々のノウハウを投入して地域資源に付加価値を与える「6次産業化」を試みる実験として推進することを目的としました。今回は私自身が実践者として、仕入れから下ごしらえ、燻製、販売までを一人で行い、モデルケースとしての可能性を検証しました。今後はこの実践を学生が自主的に企画・運営し、現場で新規商品・サービスから経営・ビジネスを体験する実践型フィールドワークへ発展させる方針としました。
2.実施概要
実施日:2025年8月13日~15日
場所:蒜山高原 道の駅「風の家」



3.実施環境
三日間とも快晴で酷暑となりました。開店直後(8時半)は販売コーナー(約300名収容)がほぼ満員となり、危険なほどの混雑になりました。人の入れ替わりが続き、10時~11時には野菜が半減し、15時には主要な野菜がほぼ完売しました。
休憩コーナー周辺の食べ物屋台は、アマゴ(渓流魚)の塩焼きとシイタケのから揚げの2店舗のみでしたが、いずれも近隣エリアからの出展でした。今回、私の「燻製や」を加えることで屋台は3店舗となり、蒜山の資源に都市のノウハウを掛け合わせた新たな6次産業化の実証となりました。
4.販売の経過
(1)1日目
10時より販売を開始しました。試食を中心に燻製たまご(200円)を訴求しました。子どもたちに大人気となり、用意した100個のうち半数近くが試食で消費されました。売上は控えめでしたが、子どもとの交流や、道の駅スタッフ・他店舗への提供により認知度向上を達成しました。

(2)2日目
ちくわ・大山ソーセージを追加してラインナップを拡大しました。午前は子どもの試食行列でにぎやかになり、夕方以降は大人層の土産購入が増加しました。顧客層によるニーズの違いを確認しましたが、売上は微増にとどまり、戦略転換の必要性を認識しました。

(3)3日目(戦略転換)
酷暑で人通りが少なく、客数の増加は期待できないと判断しました。そこで戦略を「客数拡大」から「客単価向上」へ切り替えました。燻製たまごは数量を60個に減らし、ちくわ・カニカマ・チーズ・平天を強化しました。
さらに「燻製たまごはありますか?」と聞かれた際に、燻製器の蓋をその場で開け、煙と香りを立ちのぼらせながら「今ちょうどこんな感じです。少し浅いですが、購入されます?」と実演しました。この演出をきっかけに予約販売が始まり、「もう少しいぶしてください」という要望を受け、20分後に「3個ください」「5個ください」とまとめ買いが生まれました。続けて「じゃあ、ちくわも」「ウインナーも一緒に」と購入が広がり、客単価が自然に向上しました。
試食も、ちくわ・カニカマ・チーズ・平天に集中させて購買意欲を高め、売上は前日比1.7倍を達成しました。結果として、用意した60個の燻製たまごも完売しました。ここで改めて、「売上=客数×客単価」という基本戦略の重要性を再認識しました。
さらに嬉しいことに、2015年9月3日に実施した鳥取市雇用創造協議会主催の「6次産業化と販路開拓・拡大支援セミナー」をご受講いただいた旭ビル管理株式会社中村社長がご来店・差し入れを戴き、人の繋がりの大切さを痛感いたしました。中村社長ありがとうございます。




5.成果と学び
(1)収益面
三日間の結果はほぼトントンとなりましたが、大きな赤字を回避し、採算性と可能性を確認しました。
(2)販売ノウハウ
目の前での実演(見せる・香らせる・味わってもらう)が強い訴求力を持つことを確認しました。また、チーズの燻製の人気が高かったことも考慮し、以下の戦略を提案します。
- 燻製器を3台とし、1台は、温度を低い目にし、チーズの燻製を専門に製造する。(完成まで、20分程度)
- 2台目は、今回人気のちくわ、かまぼこ、ソーセージ、ベーコン等の「串やき燻製」を製造する。(完成まで、30分程度)
- 3台目は、メインの「燻製卵」を専門に製造する。(完成まで、60分程度)
「燻製卵」は、前日に茹で上げ、空っぽの冷蔵庫で一晩乾燥させる。そして燻製時間は1時間と手間がかかります。
また、要員は最低2名が必要で、可能ならば3名がベストと考えます。後、夏場、特に酷暑は避け、秋以降の販売をお勧めします。売り上げは、燻製器を3台設置した場合、1日あたり6万円~8万円程度が見込めると考えます。
ゆで卵を製造し、一晩冷蔵庫で乾燥する仕事を、1個80円程度で地元のお母さまに依頼できると製造プロセスが楽になります。ちくわ、ソーセージは、下ごしらえも簡単で、30分程度で燻製が完成します。特に、今回の実験で、細いちくわ、カニカマは絶品でした。
(3)顧客理解
子ども中心の試食タイムでの交流は楽しく、夕方には大人中心のお土産需要が増加しました。時間帯と顧客層による購買行動の変化を把握しました。
(4)オペレーション
実演販売の魅力を保ちながら、製造・販売プロセスの効率化が持続的な課題であることを明確にしました。
(5)教育的意義
汗を流し、煙に包まれながら「美味しい」と言っていただく実体験が重要でした。この体験をベースに、教室やオンラインで学生に伝え、学生主体の実践教育へつなげたいと考えます。今回作成した「実施計画書」、「実施報告書」、「収支報告書」は、教材としての活用を意識し作成しました。
6.今後の展開
秋以降の涼しい季節は、売上拡大の余地があると見込みます。今後は、私ではなく学生が中心となり、農家・地域・都市ノウハウの協働で6次産業化を推進したいと考えています。さらに、蒜山高原に限らず、日本各地域の「ステキ、美味しい」を持続可能な事業へ発展させたいと考えています。
株式会社ワイドブックとしては、企画・コンサルティング等を担い、地域や学生の活動を支援していきます。
7.謝辞
ご協力いただいた道の駅スタッフや地域の皆様に、心より感謝申し上げます。

2025年8月16日
株式会社ワイドブック
代表取締役 廣本寿夫
(ワイドブック蒜山グリーンフィールドにて)